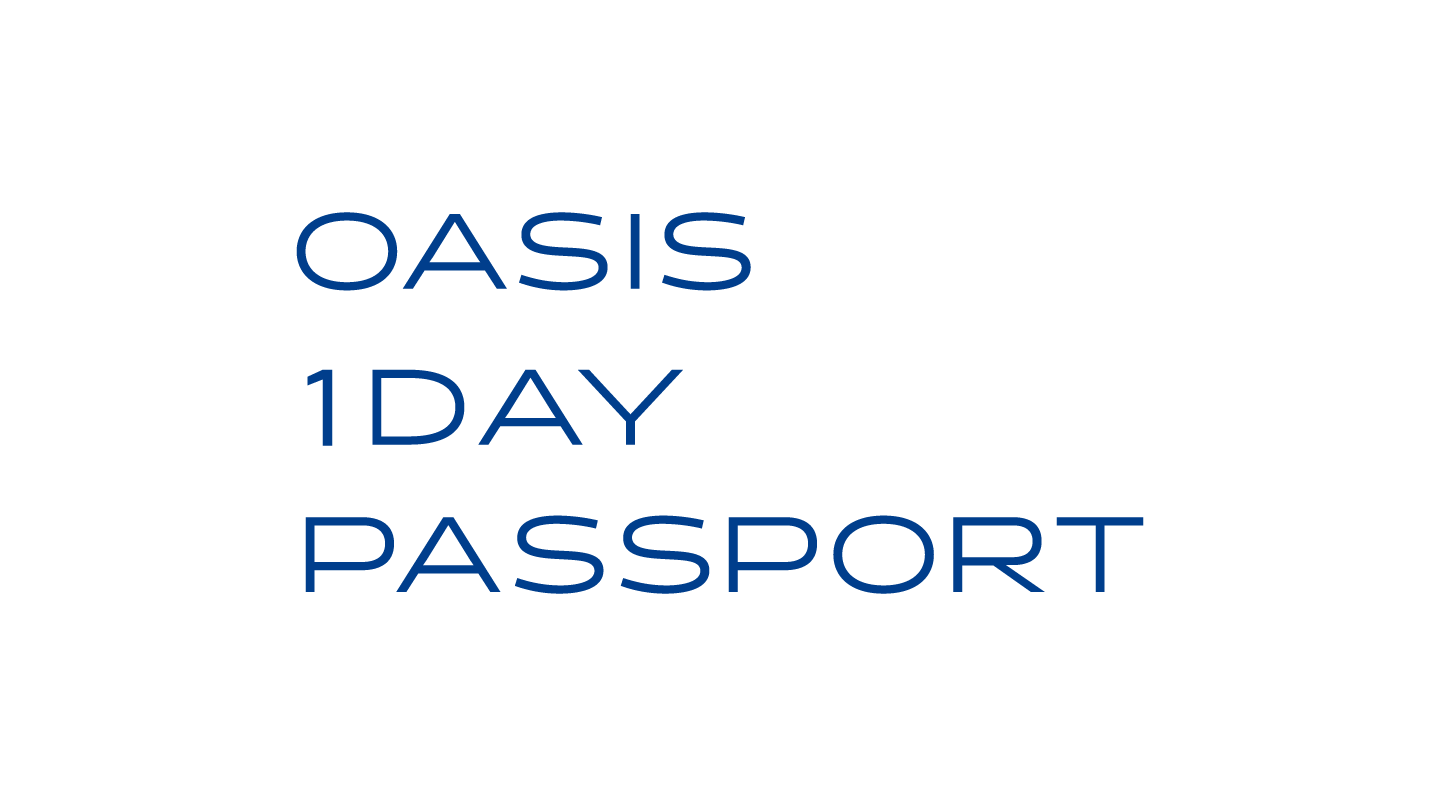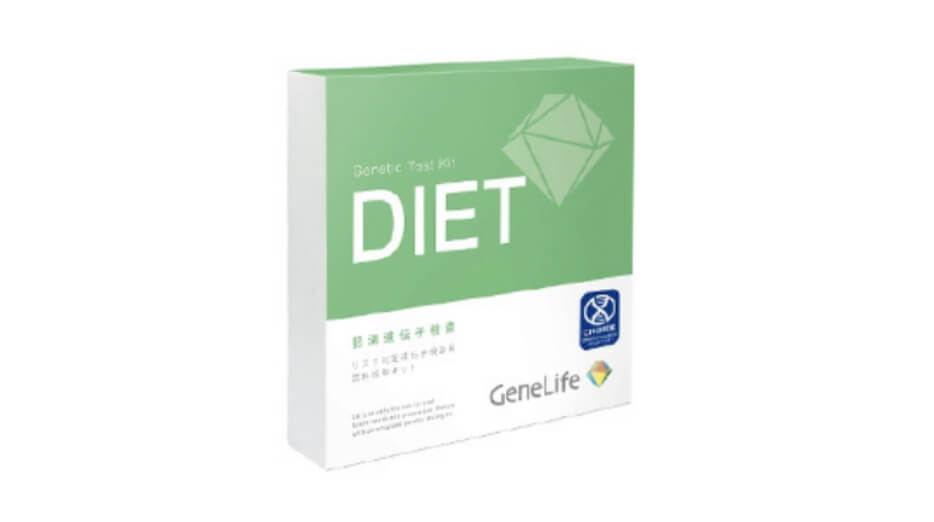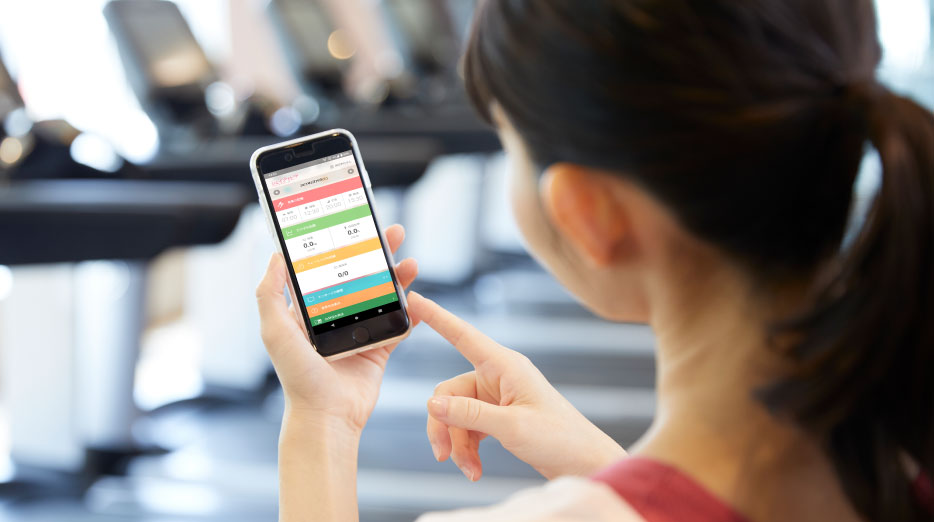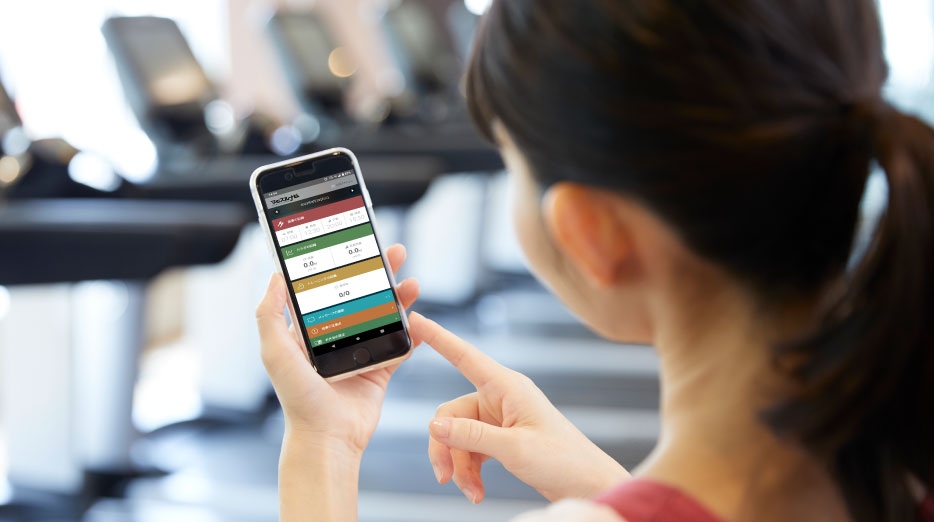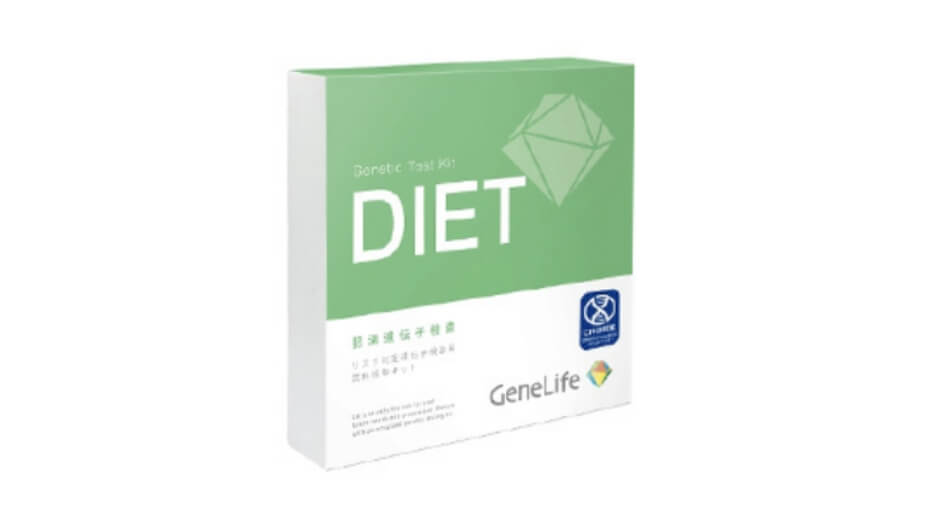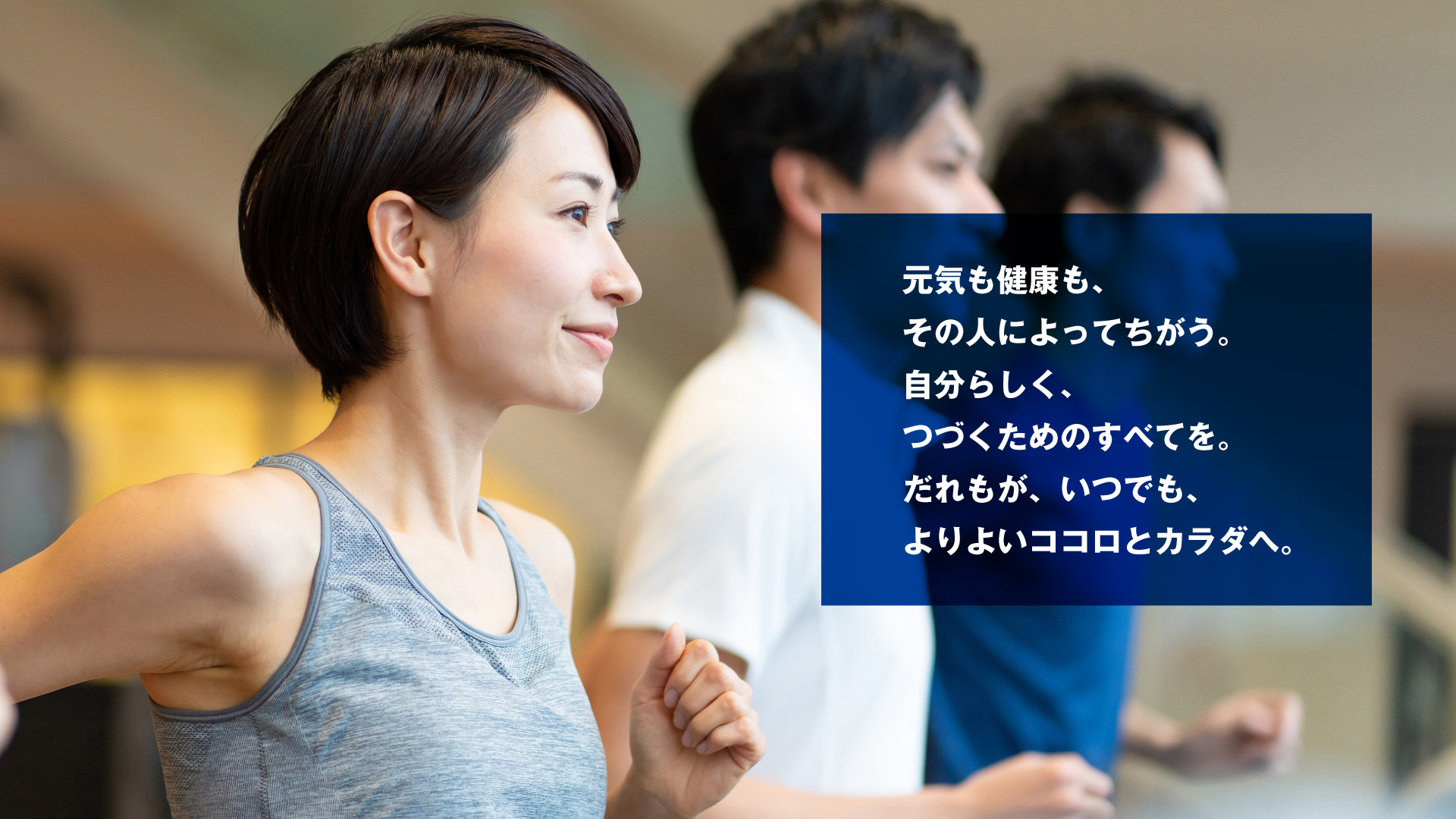
Fitness-Club
フィットネス事業
元気も健康も、
その人によってちがう。
自分らしく、
つづくためのすべてを。
だれもが、いつでも、
よりよいココロとカラダへ。
SCROLL
Fitness-Club フィットネス事業
自分らしく、つづくためのすべてを。
トレーニングや日々の活動量を管理できる
オリジナルアプリの利用や、
遺伝子検査を活用した
効果的にカラダづくりプログラム、
24時間店舗の新設など、
お客様のWell-beingをサポートする
総合フィットネスクラブです。

NEWS ニュース
CLUBS 店舗
アイコンの説明
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
関東エリア
TOKYO
-
多摩川
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
新宿24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
青山
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
武蔵小金井
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
聖路加ガーデン
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
金町24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
南大沢24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
十条24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
本駒込
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
雪谷24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
RAFEEL恵比寿24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
赤塚24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
SAITAMA
CHIBA
KANAGAWA
-
武蔵小杉24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
横須賀24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
港北
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
関西エリア
OSAKA
-
江坂24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
茨木24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
梅田
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
あべの24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
狭山24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
もりのみやキューズモール
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
-
住道24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
KYOTO
-
桂川24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ
HYOGO
-
住吉24Plus
- 24時間営業
- ジム
- スタジオ
- プール
- HOTヨガスタジオ
- 温室
- サウナ
- キッズ
- ボディケア/エステ